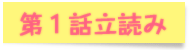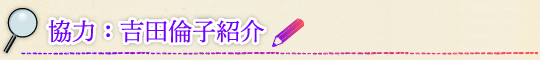吉田倫子
「マンガ『夜明けの図書館』に関わって~監修者の打ち明け話」
吉田倫子(日本図書館協会認定司書第1090号、公共図書館職員)
早いもので、『夜明けの図書館』(埜納タオ著、双葉社、既刊4巻)のお手伝いを始めて4年以上が経過した。きっかけは1巻が出た直後に、作者の埜納タオさんがカレントアウェアネス掲載のインタビュー(参考文献1)で「続編を制作するにあたり,取材やアドバイス等にご協力いただける頼もしい図書館員の方を探しています」とおっしゃっているのを読んだことである。埜納さんのブログにメールを送ったところ、担当編集者からご連絡をいただいてお付き合いが始まった(ちなみに、当初手を挙げた関係者は二人、現職の司書は私だけと言われ、図書館員の奥ゆかしさを痛感した)。
○担当編集者を間に入れる理由
当初最も気を付けたのは作家さんとの距離の取り方で、作品についての基本的なやり取りは、必ず担当編集者を通して行っている。これは、過去の作家とのやりとりの経験から考えたことである。一つは図書館団体主催のとある作家の講演会の質疑応答の経験。既に図書館界からの作品に対する批判にナーバスになっていた作家が、会場からの質問に気分を害して席を立ってしまった現場に居合わせたことがあって、生身の作家のナイーブさに驚いた記憶があるのだ。もう一つは、学校図書館を舞台にした小説を、作家が図書委員や学校司書と一緒に作るプロジェクトに関わったこと。担当の編集者を間に入れず、複数の人の多様な意見を直に一人で受け止めるその作家のメンタルのタフさに内心舌を巻いていたのだけれど、だんだんその人が書けなくなっていったのを目の当たりにした。もちろん書けなくなった原因は他にもあるのだろうけれど、現場は、現実はこうである、というたくさんの提案や意見を直接受け止めすぎたことが、自由に作品世界を動かす作家の創造の翼を縛ってしまった、という部分はやはりあったのではないか…と考えさせられた。
そこで、本作をお手伝いするにあたっては、編集者というフィルターを通すことで、作家に届く情報をコントロールしようと考えた。内容だけでなく時期や情報量など、作家の性格や状態、タイミングも鑑みて、何をいつどう渡すのがよいかを最も分かっているのは担当の編集者のはずであり、やり取りの全てをその人(増尾さん)に委ねることにしたのだ。それが功を奏したのかどうか、現在まで長く伴走することができ、チームとしての信頼感も強く醸成されてきているように思う。また、作品内容についての直接の助言だけでなく、帯コメントの募集や講演会の調整、取材先の選定についての相談やアテンドなど、お手伝いの範囲が広がっていったのも、作品にまつわって発生する様々な業務を行っている、担当編集者とのコラボあってのことだと思う。この場を借りて、いつも細やかな心遣いをいただいている増尾さんに心から御礼を申し上げたい。
○作品への助言あれこれ
最初の頃のお手伝いの様子については「みんなの図書館」で少し書いた(参考文献2)が、その後も回を追うごとに深く関わるようになり、最近ではキャラクター設定やプロットの段階から見せていただいている。そうしたやりとりの中で、"ある言葉や事象、事物が気になる"という埜納さんの発想から、それを調べるにはどんなルート(ミスリードも含めて)があるか、複数の可能性を私が説明する段階がある。
第9話(第3巻の1話目)で、"すずなり星"(昴の広島弁)をどう探すか、というお題をいただいた時のこと。レファレンスとしての最速で最短の正解は「海外の定番の星の事典を見ても出て来ず、日本的な名称であるという気づきから『日本国語大辞典』を見て記述を発見する」だったのだが、それだとエンターティンメント性に欠ける(もっと紆余曲折がないとレファレンスの物語としての盛り上がりがない)ので、「ひなこと奏太のやりとりから、司書がそのことばが方言である可能性に気づき、『日本方言大辞典』を見る」というルートが採用となった。レファレンスとしての最適解が物語を作る上での最適解とはならないこと、レファレンスにはいくつも解明に至る道があるが、どのルートを通るかでストーリーがガラリと変わるということに気づいた時、面白いな…と思った。
また、この回では実在書名の使用と出典の明記を提案した。ちょうど当時流行っていた『ビブリア古書堂の事件手帖』は書名だけでなく版や出版社まで正しく使い、それが事件の鍵を握るのも面白さの要因となっていた。しかし、本作では鍵を握る本が架空であることが多く、以前から気になっていたのだ。そこで、「『日本方言大辞典』や『日本の星 星の方言集』(野尻抱影)はこれ以外にはあり得ない!という名著たちなので、本へのリスペクトを込めて実在の本を使ってほしい。そうすれば読者の知識も深まるし、マンガとしての格もあがるはず」とお願いし、その後は実在の資料も登場するようになった。
第12話(鉄道の未成線探索で公文書館へ照会する話)では、話の主軸をレフェラル・サービスに置くことを提案した。「その資料は自館にはない。うちではできない」となった時に次の相談機関にいかに上手につなげるかも司書の腕の見せ所であること。図書館とは、そうした知のネットワークの最も市民に近い窓口であり、資料はなくともそうした知の網を知り、その使い方を市民に伝えること(=レフェラル・サービス)も、大事な仕事であることを、まだ新米のひなこに実感して欲しかったし、物語を通して読者にも伝えたかったのだが、うまくできていただろうか?
そのほか、プロットに絡めることのできる図書館界の旬のトピックスがある時は提案するようにしている。例えば第7話の歴史的音源や第11話の医療・健康情報サービス、第14話のレファレンス協同データベースなどがそれにあたる。廃棄選定や蔵書点検など自分の経験で説明できることもある一方で、私以外の人の話を聞いた方がいいな、と思うこともある。第15話の非常勤職員の小桜さんには、フェイスブックで私と繋がっている非常勤職員の経験と想いが投影されている。第14話の十団子は静岡県立図書館の知り合いにお願いして模擬回答を作成してもらった。第16話では、調布市立図書館を紹介して障害者サービスの真髄とマルチメディア・デイジーに触れていただいた。本当にたくさんの方に協力していただいたし、今後もお世話になると思うので、お友達の皆様、よろしくお願いいたします!
○司書として、作者と編集者を支える
お手伝いしていて思うのは、物語を作るという行為はとても孤独で、繊細で、苦しい作業であるということ。そして、作家さんは常に書いた作品への反応をとても気にされているということ。だから私は、それでは噓になってしまうと思った時だけ軌道修正し、基本的にはその方向で大丈夫だと声をかけて伴走を続けている。この話の監修をしているというと、もっと先端的なことを書いた方がいいとか、このサービスを書いてはどうか、など様々なアドバイスをいただくが、「次回はこのネタでいきましょう」という誘導は極力行わないようにしている。物語はあくまで作家さんのものだからだ。考えようによっては、これも課題を抱えた現場へのエンベデッド・ライブラリアン的なかかわり方なのかもしれない。
第16話のディスレクシアの少年の物語を作る際、私が埜納さんと編集さんに送った以下のメール文が、最もこうした姿勢を物語っていると思うので引用する。
今、ディスレクシアの子どもへの関りという面で、日本の公共図書館は大変遅れていることを、ひなこも、私たちも、まずは理解することが重要なのではないでしょうか?知らないこと、やっていなかったことをいきなりできたように書くことは、きっと嘘になります。けれど、自分たちがどんなに遅れているか、今まで何もしてこなかったかを知ること、その上で最初の一歩を踏み出す姿を描くことは、ディスレクシアに対する日本の図書館サービスの夜明けを描くことにほかならないのではないでしょうか。「できないこと」を理解しないと、できるようにはならない。これほど、第4巻の巻末を飾るにふさわしい話はないとも思います。私もまだ知らない、新しい明日の図書館への道を、指し示してください。それが、想像力の翼を持った「お話」の役割だと思います。
<参照文献>
1)「マンガ『夜明けの図書館』の作者・埜納タオさんインタビュー」カレントアウェアネス-E,No.207, 2011.12.22(http://current.ndl.go.jp/e1252)
2)「『夜明けの図書館』の著者、埜納タオ先生に聞く!」みんなの図書館2014年5月号(No.445)